| |
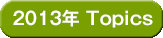











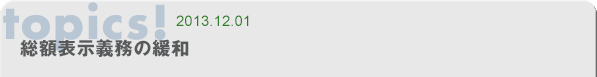 |
 |
�@����26�N4���y�ѕ���27�N10����2��ɂ킽�����ŗ������グ����\��ł����A���̈��グ�ɍۂ��A����ł̉~�����K���ȓ]�ł��m�ۂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA����25�N6��5���ɁA�u����ł̉~�����K���ȓ]�ł̊m�ۂ̂��߂̏���ł̓]�ł�j�Q����s�ׂ̐������Ɋւ�����ʑ[�u�@�v���������܂����B�����͂��̒��ŁA���i�\���Ɋւ�����ʑ[�u�ɂ��Ă��Љ�����܂��B
���T�v��
�@���݁A����҂ɏ��i�̔̔���T�[�r�X�̒��s���ېŎ��Ǝ҂ɂ́A����҂ɑ���u�l�D�v��u�L���v�Ȃǂɂ����ĉ��i��\������ꍇ�ɁA����ő����z���܂x�����z�̕\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���z�\���`��������܂��B���ƐŎ��Ǝ҂⎖�ƎҊԂ̎���ɂ͑��z�\���`���͂���܂���B
�������A����ő��łɂ��A���Ǝ҂̒l�D�̕ύX���ł̃R�X�g���⎖�����S���y�����邽�߁A����̓��ʑ[�u�@�̐����ŁA���z�\���ł͂Ȃ��A�O�ŕ\�����ꎞ�I�ɔF�߂��邱�ƂƂȂ�܂����B�܂��A�ō����i�ɕ����āA�Ŕ����i��\������ꍇ�A�ō����i�����Ăɕ\������Ă���Ƃ��́A�i�i�\���@��S ���P���i�s���\���j�̋K��͓K�p���Ȃ����ƂƂ���܂����B
�����z�\���A�O�ŕ\���̗၄
| (���z�\���̗�)�@ |
|
�@(�O�ŕ\���̗�) |
10,800�~(�ō�)
10,800�~(�Ŕ����i10,000�~)
10,800�~(��������Ŋz��800�~) |
→
���� |
10000�~(�Ŕ�)
10000�~+��
10000�~+800�~(��) |
�@���̂悤�ɑ��z�\������O�ŕ\���̕\�����F�߂��܂����B
�������A�O�ʼn��i�ŕ\������ꍇ�́A�u���ɕ\�����鉿�i���ō����i�ł���ƌ�F����Ȃ����߂̑[�u���u���Ă���v�Ƃ����v�������K�v������܂��̂ŁA�X���̖ڗ��ꏊ�Ɂu���X�̏��i�͑S�ĐŔ��\���ƂȂ��Ă���܂��B�v���̕\��������K�v������܂��B
���K�p���ԁ�
�@�����ʑ[�u�@�̓K�p�͕���25�N10��1�����畽��29�N3��31���܂łƂȂ�܂��B����ő��Ŏ����̕���26�N4��1���ȑO���K�p���F�߂��܂��̂ŁA�]�T�������ď����Ɏ��|���邱�Ƃ��őP�ł��B
�S���@�N�� ���G |
|
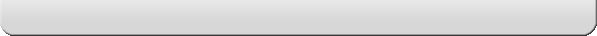 |





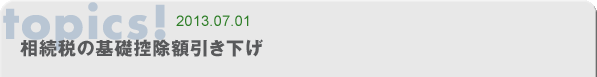 |
 |
�@�����͕���25�N�x�Ő������̂����A�����ł̊�b�T���z���������ɂ��Ă��Љ�����܂��B
���T�v��
�@�����ł́A�e���Ȃǂ��S���Ȃ������Ƃɂ����Y��O�̑ォ��p�����ꍇ���ɔ�������ŋ��ł��B
���̑����łł����S�ẴP�[�X�ő����ł���������̂ł͂Ȃ��A����������Y�̑��z�����z�i��b�T���z�j����ꍇ�̂݁A�\�����đ����ł�[�߂�Ƃ����d�g�݂ɂȂ�܂��B��������ł́A����27�N�P��1���ȍ~�ɔ������������ɂ��āA���̊�b�T���z�������������邱�Ƃ����肵�܂����B�]���ł͑����ł̔[�t�`������������̂�100�l����4���ƌ����Ă���܂������A������͔{�����錩�ʂ��ł��B���̂��߁A���܂ő����łƂ͖������������ł��A������̕K�v�����o�Ă���\��������܂��B
����b�T���z�̉�����
�@����̉����ɂ�蕽��27�N�P��1���ȍ~�̊�b�T���z�����s��60���Ɉ����������܂��B
| ���@�s |
5,000���~+(1,000���~×�@�葊���l�̐�) |
| ������ |
3,000���~+(600���~×�@�葊���l�̐�) |
�@�@�葊���l���A�z���1���Ǝq��2���̍��v3���̏ꍇ�ł͊�b�T���z�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
| ���@�s |
5,000���~+(1,000×3��)��8,000���~ |
| ������ |
3,000���~+(600���~×3��)��4,800���~ |
�@ ����āA������ł͊�b�T���z��3,200���~�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@��L�̃P�[�X�ŖS���Ȃ����l�i�푊���l�j���ȉ��̂悤�ȍ��Y�����L���Ă��Ă����ꍇ�ɂ́A�]���ł͑����ł̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���ł������A������͑����ł̐\�����K�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�@
�@ �Ō�ɂȂ�܂����A�u�z��ҍT���v��u���K�͑�n���̓���v�Ȃǂ̐��x�𗘗p���邱�ƂŐ\���݂̂��s���A�ŋ��͔������Ȃ��ꍇ������܂��B���^������������������ꍇ�ɂ́A�����߂ɒS���҂ɂ����k���������B
�S���@�����@���j |
|
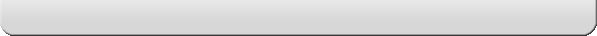 |

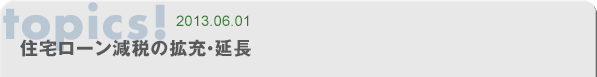 |
 |
�@����25�N�Ő������@��3��29���ɐ������܂����B�����͂��̂����̏Z��[�����ł̊g�[�E�����ɂ��Ă��Љ�����܂��B
�������̎�ȊT�v��
�E����25�N�x���ŏI���\��̌��s���x��4�N�ԉ���
�E����26�N4�����e�N�̍T�����x�z��20���~����40���~�Ɉ����グ
�@���F��Z��(�F�蒷���D�ǏZ��y�єF���_�f�Z��)�ɂ��Ă�30���~����50���~�Ɉ����グ
�E����26�N4�����10�N���v�̍ő�T���\�z��200���~����400���~�Ɉ����グ
�@���F��Z��(�F�蒷���D�ǏZ��y�єF���_�f�Z��)�ɂ��Ă�300���~����500���~�Ɉ����グ
�E�����ł���T��������Ȃ������z�̏Z���ł���̍T�������x�z97,500�~����136,500�~�֑��z
�E���Ȏ����ŏZ����w�������ꍇ�̍T�����x�z��50���~����65���~�Ɉ����グ
���L�\�͔F��Z��ȊO�̏Z����w�������ꍇ�̏Z��[�����ł̕ύX���e�ƂȂ�܂��B
���Z�J�n
�N���� |
�N���c����
���x�z |
�T���� |
�e�N��
�T�����x�z |
�ő�T��
�\�z |
�T������ |
�Z���ł����
�T�����x�z |
����
(����25�N)�@ |
2,000���~ |
1% |
20���~ |
200���~ |
10�N |
�����ł̉ېŏ������z×5��
(�ō�9.75���~) |
����26�N
1�`3�� |
2,000���~ |
1% |
20���~ |
200���~ |
10�N |
�����ł̉ېŏ������z×5��
(�ō�9.75���~) |
����26�N4���`
����29�N12�� |
4,000���~ |
1% |
40���~ |
400���~ |
10�N |
�����ł̉ېŏ������z×7��
(�ō�13.65���~) |
�������̖ړI��
�@�Z��擾�ɂ��Ă͎�����i�����z�ł���A����26�N4������̏���ő��łɔ����Z��擾�҂̕��S���y�����邽�߁A�܂��A����ő��łɂ��삯���ݎ��v�y�т��̔�����}���邽�߂ƌ����Ă��܂��B
���V�~�����[�V������
�@����25�N�x���ɋ��Z���J�n�����ꍇ�Ə���ő��Ō�ɏZ��w���y�ы��Z���J�n�����ꍇ�Ƃŏ���ő��łɂ�镉�S�����z�ƍ���̉���(�e�N�̍T�����x�z��20���~����40���~�ɑ����A�y�яZ���ł���̍T�����x�z�̑��z)���s��ꂽ�ꍇ�̌��ő����z�ɂ��ƌv���S�����z���e�A�����E�ؓ��z�ʂɎ��Z���܂����B
�y�P�[�X�@�z
�E�N���F500���~�@�E�Ƒ��\���F�z���1�l�E16�Έȏ�}�{�e��1�l�@
�E�ؓ����z�F2,500���~(�ԍϊ���35�N�A�����ϓ��ԍ�)�@
�E�Z��y�ѓy�n�擾���i�F3,000���~(�Z��i1,800���~)�@
| �@ |
�N�� |
500���~ |
| �A |
�ؓ��z |
2,500���~ |
| �B |
�Z��i |
1,800���~ |
| �C |
����łɂ�镉�S�����z�@�B×3�� |
��54���~ |
| �D |
�e�N�̍T�����x�z20���~����40���~�ւ̈����グ�A
�y�яZ���ł���̍T�����x�z���z�ɔ������ő����z(10�N���v) |
��21���~ |
| �E |
�ƌv���S�����z�@�C−�D |
��33���~ |
�y�P�[�X�A�z
�E�N���F800���~�@�E�Ƒ��\���F�z���1�l�E16�Έȏ�}�{�e��1�l
�E�ؓ����z�F4,000���~(�ԍϊ���35�N�A�����ϓ��ԍ�)�@
�E�Z��y�ѓy�n�擾���i�F4,500���~(�Z��i2,700���~)
| �@ |
�N�� |
800���~ |
| �A |
�ؓ��z |
4,000���~ |
| �B |
�Z��i |
2,700���~ |
| �C |
����łɂ�镉�S�����z�@�B×3�� |
��81���~ |
| �D |
�e�N�̍T�����x�z20���~����40���~�ւ̈����グ�A
�y�яZ���ł���̍T�����x�z���z�ɔ������ő����z(10�N���v) |
��153���~ |
| �E |
�ƌv���S�����z�@�C−�D |
��−72���~ |
�@���ۂ̔N���ɑ���ؓ����z�A�Z��i���̋��z�͊e�ƒ�ɂ��قȂ�܂��̂ŁA��T�ɂ͌����܂��A��L���Z����y�P�[�X�@�z�N��500���~�̉ƒ�ł́A����ő��Ō�ɏZ��w���E���Z�����ꍇ�́A����ő��łɂ�镉�S�z54���~����Z��[�����ł̉����ɂ�錸�Ŋz21���~�E���Ă���33���~�̕��S���ƂȂ����ő��őO�ɏZ��w���E���Z���������L���ƂȂ�܂��B
�@����y�P�[�X�A�z�N��800���~�̉ƒ�ł́A����ő��Ō�ɏZ��w���E���Z�����ꍇ�́A����ő��łɂ�镉�S�z81���~����Z��[�����ł̉����ɂ�錸�Ŋz153���~�E����Ɩ�72���~������v�Z�ƂȂ�A����ő��Ō�ɏZ��w���E���Z���������L���ƂȂ�܂��B
�@�ȏ�̌��ʁA�N�������z�ȉƒ�͓������ɂ�鉶�b���邱�Ƃ��ł��܂����A�Z��[�����p�҂̍ł������Ƃ�����N��400���~�`600���~�̉ƒ�ɂ����Ă͏���ő��őO�ɏZ��w���E���Z�����������S�͏��Ȃ��Ȃ�v�Z�ƂȂ�܂��B
�������A�������ɂ����Ă͒x���Ƃ����Ă܂łɏZ��[�����ł̊g�[�[�u���u���Ă��Ȃ����ʂ�����I�ȏ����w�ɑ��ēK�ȋ��t�[�u���u���邱�Ƃ����荞�܂�Ă���܂��̂ō���̐Ő������Ŏ����̍��ɂ�铖�����̉��b�̊i���͂Ȃ��Ȃ�\��������܂��B
�S���@�N��@���G |
|
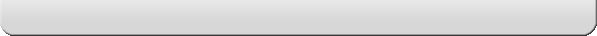 |

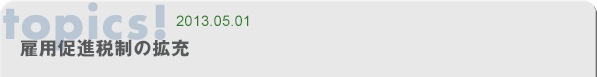 |
 |
�@����25�N�Ő������@��3��29���ɐ������܂����B����͌ٗp���i�Ő��̉������e�����ē������Ă��������܂��B�Ȃ��A���̌ٗp���i�Ő��͐挎���Љ���u�����g�呣�i�Ő��v�Ƃ̑I��K�p�ƂȂ�܂��B
���������e��
�@�@�ٗp�ҁi�ٗp�ی���ʔ�ی��ҁj��������2�l�ȏ�i���Ƃ�5�l�ȏ�j���̈��̗v�������ꍇ�ɁA����Ŋz�T���z���ٗp������1�l������40���~�i���s20���~�j�Ɉ����グ���܂��B�Ȃ��A�@�l�Ŋz��20���i���Ƃ�10���j�̍T�����x�z�ɂ��Ă͏]���ƕύX�͂���܂���B�K�p���ƔN�x�́A����25�N4���ȍ~�ɊJ�n���鎖�ƔN�x���ΏۂƂȂ錩�ʂ��ł��B
���K�p�v����
�ٗp���i�Ő��̐Ŋz�T�����邽�߂ɂ́A�ȉ���5�̗v�������ׂĖ������K�v������܂��B
�@ �O���y�ѓ����Ɏ��Ǝ�s���ɂ�闣�E�҂����Ȃ�����
�O���y�ѓ����Ƀ��X�g�����̉�Гs���ɂ�闣�E�҂�����ꍇ�ł���A�]�ƈ��̎��ȓs���ɂ��ސE�͖�肠��܂���B
�A ��ٗp�Ґ���2�l�ȏ�i���Ƃ�5�l�ȏ�j�ł��邱��
��ٗp�Ґ��Ƃ́A�������̌ٗp�Ґ�����O�����̌ٗp�Ґ����������l���ɂȂ�܂��B
�܂��ٗp�҂Ƃ́A�@�l�̎g�p�l�̂����ٗp�ی��̈�ʔ�ی��҂̂��ƂŁA�����͏������ق��A�]�ƈ��ł����Ă������̐e���Ȃǖ����Ɠ���W�ɂ���ғ��͏�����܂��B
�B ��ٗp������10���ȏ�ł��邱�� �@
��ٗp�����Ƃ́A��ٗp�Ґ���O�����̌ٗp�Ґ��ŏ��������ł��B
�C ���^���x���z����r���^���x���z�ȏ�ł��邱��
���^���x���z�Ƃ́A�����̋��^�̎x���z�ł��B
��r���^���x���z�Ƃ́A���̎Z���ɂ��v�Z�������z�ł��B
�@�O���̋��^���̎x���z�{�i�O���̋��^���̎x���z×��ٗp�Ґ�����×30���j
�D �ٗp�ی��̓K�p���Ƃ��s���Ă��邱��
�����ƂȂǂ̎��Ƃ͓K�p�ΏۊO�ƂȂ�܂��B
���P�[�X�X�^�f�B��
���Ɗg��̂��߁A������Ƃ�����ɏ]�ƈ���V�K2���̗p�����ꍇ���Љ�܂��B
| �O���� |
������ |
�ٗp�Ґ��F10��
���^���̎x���z�F30,000,000�~ |
�ٗp�Ґ��F12��
���^���̎x���z�F36,000,000�~ |
�@ ���Ǝ�̗��E�҂����Ȃ����ƁA�y�сA�D�ٗp�ی��̓K�p���Ƃł��邱�Ƃ�O��Ƃ��܂��B
�A ��ٗp�Ґ�
����̊�ٗp�Ґ��́A12���|10����2���@�ƂȂ�2���ȏ�̂��ߗv�������܂��B
�B ��ٗp����
��L�Ōv�Z������ٗp�Ґ���2����O�����̌ٗp�Ґ�10���ŏ����܂��B
2��÷10����0.2��20���@�ƂȂ�10�����邽�ߗv�������Ă��܂��B
�C ���^���x���z�̔�r
���^���x���z�́A36,000,000�~�ł��B
��r���^���x���z�́A�B�̊�ٗp����20���𗘗p���Čv�Z���܂��B
�@30,000,000�~�{�i30,000,000�~×20��×30���j��31,800,000�~
���^���x���z����r���^���x���z�ȏ�̂��ߗv�������܂��B
�@��L�̒ʂ�A�S�Ă̗v���������ꍇ�ɂ́A2��×40����80���~�i�@�l�Ŋz��20��������j�̐Ŋz�T�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���ۂɂ��̌ٗp���i�Ő��̓K�p�������������ꍇ�ɂ́A���O�ɒS���҂܂ł��A�����������悤���肢�v���܂��B
�S���@�����@���j |
|
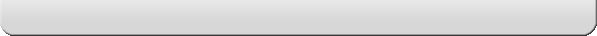 |



 |
 |
�@���R����}�A�����}���}��1��24���Ɂu����25�N�x�Ő�������j�v�\���܂����B���L�ɐŖڂ��ƂɃ|�C���g���܂Ƃ߂܂����B
�P�D�@�l��
| ���� |
���e |
�K�p���� |
������ƌ��۔�
�i���Łj |
�@��z�T�����x�z��800���~�Ɉ����グ���ƂƂ��Ɂi���s600���~�j�A��z�T�����x�z�܂ł��S�z�������Z���ƂȂ�i���s��10%�͑����s�Z���j |
H25.4.1�ȍ~�J�n�̊e���ƔN�x |
���^�x�����g�[
�i���ŁE�V�݁j |
�@�F�\���@�l���A�����ٗp�҂ɑ��ċ��^�����x������ꍇ�A���L�Z���̊�����5%�ȏ�ł���Ƃ��́A�ٗp�ҋ��^���x�������z��10%�̐Ŋz�T�����ł���i�@�l�ł�10%�i������Ƃ�20%�j�����x�j�B
���Z����
�i�ٗp�ҋ��^���x���z-��ٗp�ҋ��^���x���z�j�^��ٗp�ҋ��^���x���z
����ٗp�ҋ��^���x���z�Ƃ͕���25�N3��31���ȑO���ߎ��ƔN�x�̋��^���x���z
�����̑��K�p������
�E�ٗp�ҋ��^���x���z���O���ƔN�x�������Ȃ�����
�E���ϋ��^���x���z���O���ƔN�x�������Ȃ����� |
H25.4.1�`
H28.3.31�܂ł̊ԂɊJ�n����e���ƔN�x |
2�D������
| ���� |
���e |
�K�p���� |
| �ō��ŗ��̈����グ�i���Łj |
�@���s�̏����ł̐ŗ��\���ɉ����āA�ېŏ���4,000���~���ɂ���45%�̐ŗ���݂����i���s��40%�i1800���~���j���ō��j |
H27�N���Ȍ� |
�Z��[���T��
�i���ŁE�����j |
�@�Z����擾���āA����26�N���畽��29�N�܂ł̊Ԃɋ��Z�̗p�ɋ������ꍇ�̐Ŋz�T�������̂Ƃ��艄������
| ���Z�N |
�ؓ�
���x�z |
�T���� |
�e�N��
���x�z |
���� |
H26.1�`
H26.3 |
2,000���~ |
1.0% |
20���~ |
10�N |
H26.4�`
H29.12 |
4,000���~ |
1.0% |
40���~ |
10�N |
|
H26.1.1�`
H35.12.31
�i�����J�݊��ԁj |
| ���z������ېŁi���Łj |
�@�N100���~�܂��̊����E�������M�ւ̓����ɂ��āA�z������n�v��5�N�Ԕ�ې��Ƃ���i�����Ō����J�݊��ԉ����j |
H26.1.1�`
H35.12.31
�i�����J�݊��ԁj |
3�D�����
| ���� |
���e |
�K�p���� |
�y���ŗ�
�i�����j |
����27�N10���ɏ���ŗ���10%�Ɉ����グ�������Ƃɔ����A�i�ڂɂ�����y���ŗ������邱�Ƃ�ڎw���i����26�N4����8%�Ɉ����グ����Ƃ��͂̌y���ŗ������͌�����܂����j |
H27.10.1�ȍ~ |
4�D�����E���^��
| ���� |
���e |
�K�p���� |
| �ō��ŗ��̈����グ�i���ŁE�V�݁j |
�������Y�U���~���̕����ɂ���55%�̐ŗ���݂����i���s��50%�i3���~���j���ō��j |
H27.1.1�ȍ~ |
| ��b�T���̌������i���Łj |
�@�����ł̊�b�T���z�� 3,000���~�{�i�@�葊���l�̐�×600���~�j�Ƃ���B
�����s�́@5,000���~�{�i�@�葊���l�̐�×1,000���~�j |
H27.1.1�ȍ~ |
| ���玑�����^�̔�ېŁi���Łj |
�@�q�E���i30�Ζ����j�����玑���ɏ[�Ă邽�߂ɋ��Z�@�ւɐM���������ꍇ�ɂ́A�q�E��1�l������1,500���~�܂ł̋��z�ɂ��đ��^�ł��ې��Ƃ���B |
H25.4.1�`
H27.12.31 |
| ���������Z�ېŐ��x�K�p�҂�
�g�[
�i���Łj |
�@�҂͈̔͂ɁA20�Έȏ�ł��鑷�i���s�͐��葊���l�̂݁j��lj�����B
�@���^�҂̔N��v����60�Έȏ��i���s��65�Έȏ�j�Ɉ��������� |
H27.1.1�ȍ~ |
|
|
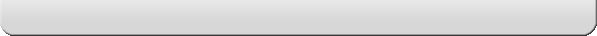 |

 |
 |
�@����i2012.7 Topics�j�̂Ƃ�������25�N1��1�����畽��49�N12��31���܂ł�25�N���Ő����鏊���ɂ��Č�������ۂɂ́A�����ł�2.1���������ł��镜�����ʏ����ł��Ē������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ�܂��i���������m�ۖ@28�j�B
�@���̌����̊J�n�����ɂ��āA���^�ƕ�V�i�ŗ��m�E��v�m���j�Ŏ戵�����قȂ�̂Œ��ӂ��K�v�ƂȂ�܂��B
�P�D���^�ɂ����镜�����ʏ�����
�@���^�����ɑ��镜�����ʏ����ł̉ېł̔��f�ɂ��āA���Œ������\�����w�������ʏ����Łi�����W�jQ��A�x�ł́A�u���N12�������^�𗂔N1���Ɏx�������ƂƂ��A25�N1���̎x�����\���24�N12�����̋��^�͕������ʏ����ł���������K�v������܂����v�Ƃ����₢�Łu�_��A���K�A���呍��̌��c���ɂ��x��������߂��Ă��鋋�^�́A���̎x���������̋��^�̎������ׂ������Ƃ���Ă��܂��v�Ƃ̎戵��������܂��B
�@�܂蕽��23�N12�������߁A�����i����24�N1���j�x�����̋��^�ɂ��ẮA�������ʏ����ł������K�v������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�Q�D��V�i�J�����}���A�f�U�C�i�[�A�ŗ��m���j�ɂ����镜�����ʏ�����
�@�ŗ��m���v�m�Ȃǂ̕�V�ɌW��������ׂ������́A�l�I�̒ɂ��������z�ɂ��ẮA�����l�I�̒��������������畜�����ʏ����ł̌����������������ƂƂȂ�܂��B
�@�������A�l�I�̒ɂ���V�����Ԃ̌o�ߖ��͖̒̒��x���ɉ����Ď���������͊��K������ꍇ�ɂ����邻�̊��Ԃ̌o�ߖ��͖̒̒��x���ɑΉ������V�ɂ��ẮA�u���̓��͊��K�ɂ�肻�̎������ׂ����R�����������v�Ŕ��肷�邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�܂�A�_�̎��������̂́A�����I�ɂ͐ŗ��m��V�̖�������25�N1���Ȍ�̏ꍇ�ɂ͂��߂āA���̖ɑ����V�ɂ��ĕ������ʏ����ł��ۂ���A�����`���҂͏����łƕ����Ē������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƂƂȂ�܂��B
�@�Ⴆ�A�_�u�������猎�����̕�V�𗂌�15������
�Ƃ��Ă���ꍇ�A1��15���̎x�����i24�N12�����i12/1�`12/31�j�ɌW��x���j�́A24�N12�����̖�������24�N12�������ł��邽�߁A�������ʏ����ł͉ۂ���Ȃ����ƂƂȂ�܂��B
�@�܂��A�_�u16�����痂��15�����𗂌���������
�ɂ��Ă���ꍇ�A1�������̎x�������i24�N12��16������25�N1��15���j�́A��������25�N1���ł��邽�߁A24�N����25�N���Ƃ����v�Z�����邱�ƂȂ��A��V�z�S�z�ɑ��ĕ������ʏ����ł��ۂ���邱�ƂƂȂ�܂��B |
|
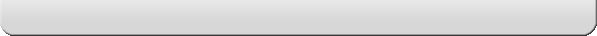 |
|

